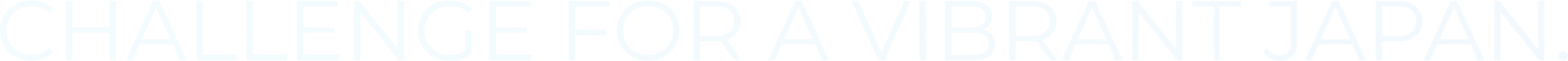
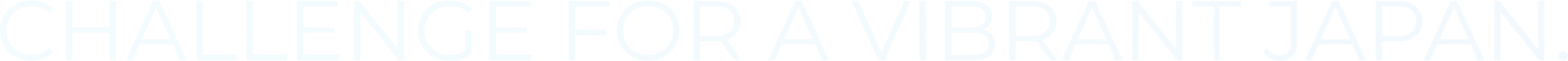
「事業承継は、経営者にとって“最後の大仕事”なんです」
──そう語るのは、グループ創業者であり代表を務める岩永。
創業以来、相続・事業承継に特化し、「日本のミライに豊かさを」というビジョンのもと、
中小企業の未来と本気で向き合ってきた。
そして今、その構想をかたちにすべく、承継アドバイザリー部門の責任者として第一線を走るのが、松下だ。
大手税理士法人での経験を経て、「本気で経営者と向き合える現場」を求めてチームに加わった実力派だ。
地域経済の土台を支え、未来に豊かさをつなぐ仕事──事業承継の本質と、
このフィールドでプロフェッショナルが成長する意義を、二人に語ってもらった。
PROFILE

岩永 悠
グループ共同代表
西南学院大学経済学部卒業。京都大学経営管理大学院 上級経営会計専門家(EMBA)プログラム修了。2007年に九州の中堅税理士法人に入社。26歳で税理士登録後、国内大手税理士法人の福岡事務所設立に参画。13年岩永悠税理士事務所として独立、15年税理士法人アイユーコンサルティングに改組し法人化。19年よりグループ化に着手し、インキュベート事業の㈱IUCG、第三者承継の手段であるM&AやIPO支援を主力事業とする㈱アイユーミライデザイン、顧問特化型の税理士法人IU Management等を設立。「日本のミライに豊かさを」をビジョンに掲げ、現在8法人1事務所体制でグループを運営している。
創業者としてグループ経営に携わる一方で、自身も組織再編を活用した高度な事業承継、相続対策を提案・実行。提案型コンサルタントとして大型案件を中心に実務を行いながら、セミナー活動や団体活動を中心に業界発展のために力を注いでいる。

松下 孝司
承継アドバイザリー部 部長
大学卒業後、広島のIT企業のシステムエンジニアとして5年ほど従事。経営者と直接話せるような仕事がしたいとの想いから一念発起し、税理士を目指す。
2013年国内大手税理士法人に入社。東京本部にて、事業承継コンサルティング及び相続税申告、その他一般税務申告業務を担当。その後、同税理士法人福岡事務所に異動し上記業務に加え、財務・税務デューデリジェンス、中小企業投資減税サポート、補助金申請サポート等、幅広い業務を経験。
2022年7月、これまで培った知識経験をより活かすべく税理士法人アイユーコンサルティングに入社。2024年1月には事業承継専門部隊である承継アドバイザリー部責任者に就任。事業承継、相続の単なる専門家としてだけではなく、時代の流れ・要請を敏感に感じ取り、様々な角度から高付加価値な提案助言を行えるコンサルタント税理士を目指し、日々邁進している。
SESSION.1
「“相続・事業承継のプロ集団”をつくりたかった」──創業時からの構想

岩永
僕は創業当時から、「相続」と「事業承継」に特化した事務所にする構想がありました。理由は、相続に特化した事務所は当時からあったものの、事業承継まで対応できる事務所は大手くらいしかなく、ブランディングの観点で差別化できると思ったから。だけど何よりも、日本の中小企業の未来を考えたとき、必ず社会に必要とされる分野だという確信があったんです。僕自身も数多くの事業承継案件に携わってきましたが、得られるやりがいも一段と大きいと感じます。

松下
僕も前職の大手税理士法人では、事業承継分野をメインに担当していました。ただ、規模が大きいがゆえに、自分が本当に納得いくまでお客様に向き合うことが段々と難しくなってきて。もっと経営者と本音で向き合うような仕事がしたい──そんな気持ちを持ち始めたタイミングで、知り合いだったグループ共同代表の出川さんから声をかけられたのが入社のきっかけです。

岩永
入社前に松下さんと一度食事をした時、その場で「やります」と即答してくれたのは嬉しかったですね。当時の福岡事務所では、相続部門の体制が整いつつある一方で、事業承継の強化が急務でした。ただ、拠点長が日々の実務やマネジメントを抱えながら、新たに事業承継案件に対応できる人材を育てるのは、やはり限界がある。そこに松下さんという即戦力が加わってくれて、「これは今が仕組み化に踏み切るタイミングだ」と思ったんです。

松下
僕が即決したのは、直感的に「ここなら本気でやれる」と感じたからです。あの時、岩永さんが「今、ここからチームをつくっていこう」と言ってくださった言葉がすごく印象に残っています。「事業承継を仕組み化する」「全国に広げていく」という明確なビジョンがあって、そこに自分が本気で関われる環境が整っている。そのスケール感とスピード感は、他では絶対に得られないと思いました。
SESSION.2
事業承継は経営者の最後の大仕事

岩永
相続が「個人」に寄り添う支援だとすれば、事業承継は「法人」、それも「オーナー」に深く寄り添う支援です。経営者として人生をかけて育ててきた事業を、誰に、どう引き継ぐのか──そこには計り知れない覚悟と、繊細な決断が伴います。僕たちはその覚悟を支える“伴走者”として、経営者と真摯に向き合う必要がある。

松下
相続単体の案件とは異なり、そこには事業の継続性や従業員の生活、取引先との関係まで複雑に絡んでくるからこそ、より戦略的で多面的な支援が求められます。しかも事業承継って、基本的に“初めて”の出来事なんですよね。経営者にとっても、社員にとっても。だからこそ、第三者の立場でフラットに話を聞きながら、感情や利害を丁寧に整理していくことが重要だと思っています。
僕自身、30代前半のころから60〜70代の経営者と本音で向き合ってきましたが、世代も価値観もまったく違う方と同じ目線で“未来のビジョン”を描いていく経験は、他の分野では得難い貴重な体験でした。

岩永
事業承継は、経営者にとって“会社人生の集大成”とも言える大仕事。それだけに、たった一度の判断ミスが、これまで築いてきたものすべてを崩してしまう可能性もある。しかも、それが数十年に1回あるかないかのタイミングで訪れる。そんな重責を担う立場にある僕たちコンサルタントの使命は、単に手続きやスキームを提案することじゃない。経営者の“意志”を正しく理解し、その意思を次世代へどうつなぐか、未来の視点で寄り添うことにあると考えています。

SESSION.3
事業承継が持つ“社会的意義”とは?

岩永
2025年には、いわゆる“団塊の世代”が後期高齢者の域に達します。これからの日本は、中小企業の経営者が大量にリタイアしていくフェーズに突入していく。ですが、後継者が決まっていなかったり、承継の準備ができていなかったりする企業が本当に多いんです。うまく事業承継が進まなければ、黒字でも廃業せざるを得ない会社が急増する。つまり、地域経済そのものが揺らぎかねないという危機的状況なんです。

松下
実際に現場に出ていると、「もっと早く相談してくれたら、違う未来があったのに」と思うケースに何度も出会います。事業承継は、決して“税金対策”や“株価対策”の話だけではありません。そこには、社長自身の人生の集大成としての「想い」がある。先代の理念をどう引き継ぎ、次の世代にどうつなぐか。その葛藤に寄り添えるのが、僕たちコンサルタントの使命だと思っています。

岩永
数字で語れる部分もありますが、この分野の本質は“人間くささ”だと思うんです。たとえば、長年苦楽を共にしてきた幹部との関係性、親族間の微妙な距離感、息子には継がせたいけど本音では反対している家族の想い──そういった“見えない課題”にどう向き合うかが、事業承継支援の難しさであり、やりがいです。

松下
まさに、AIやシステムでは解決できない、人と人の「対話」が中心になる領域ですね。最近では、技術的な支援だけでなく、「経営者が最後に誰に相談したいか」が問われているように感じます。ただ法的に正しいだけの提案では動かない。経営者の“心の奥”に踏み込めるアドバイザーこそが、最終的に選ばれる存在だと実感しています。

岩永
アイユーコンサルティンググループでは、大手のようなパッケージ支援ではなく、一社一社に本気で向き合う“オーダーメイド型”の承継支援を大切にしています。この規模だからこそできる柔軟な対応や、各専門家とのネットワークを活かして、複雑な承継案件でもスピーディーかつ丁寧な対応ができる体制がある。

松下
そこは大きな強みですよね。重要なのは単なる専門知識の積み上げではなく、「この会社と、この人たちの未来をどう描くか」。その視点がなければ、本質的な支援はできない。承継とは、単なる引き継ぎではなく、企業という組織に未来を託すこと。そのバトンをどう渡し、次の世代へつないでいくか――まさに、未来をつくる営みだと思います。

岩永
いま、事業承継は企業単体の問題ではなく、地域経済や社会全体の持続性に関わる重要なテーマになっています。雇用や技術、文化を次の世代へとつないでいくこの仕事には、目の前の支援を超えた意義がある。まさにそれは、僕たちが掲げる「日本のミライに豊かさを」というビジョンの中核をなすものです。そうした未来づくりに本気で向き合える仲間とともに、これからも挑戦を続けていきたいですね。
SESSION.4
現場で磨く、“対話力”と“自走力”

松下
事業承継の支援に必要なのは、やはり「対話力」と「判断力」だと思います。もちろん専門知識は前提ですが、それだけでは足りない。経営者の想いや家族との関係、従業員の未来など、さまざまな要素が絡み合う中で、その企業にとっての“最適解”を一緒に探していく。つまり、「どう聞き、どう引き出し、どう導くか」というコミュニケーションの力が欠かせません。

岩永
特に承継の相談では、経営者が本音を話せる相手がいないことも多い。僕たちがただ“税理士”として接しているだけでは、核心に触れる話は出てこない。だからこそ、人として信頼してもらうために自分の言葉で語り、本気で未来を描こうとする姿勢が問われます。これはマニュアルでは身につかないし、現場で鍛えるしかない力です。

松下
その通りです。だからこそ、部下にはできるだけお客様との面談に同席してもらっています。お客様の表情、声のトーン、空気感――そうした“現場”からしか学べないことがたくさんあるんです。何を聞くか、どこに踏み込むか。それを自分で考えながら動けるようになることが、この仕事の第一歩です。

岩永
加えて、やはりこの分野では「自走力」がないと活躍できません。未経験の方にはまず顧問といった基礎分野から経験してもらい、その傍ら相続も経験する。徐々にステップアップして事業承継へ、という流れをつくっていますが、それは“主体的に考え、動ける力”を育てるためのプロセスとも言えます。

松下
事業承継は、マニュアル通りにはいかない仕事です。企業の特性や経営者の価値観、親族関係や組織の文化など、見えない背景を読み解く力が必要です。「自分が主導して提案を組み立て、実行まで責任を持つ」意識を持てる人こそ、真のアドバイザーだと思います。

岩永
それに事業承継の案件は、待っていても来ないことがほとんど。明確な依頼があるというより、こちらから気づき、動き、機会をつくっていく必要がある。金融機関や士業ネットワークと連携して、新たなニーズを発掘できる力が求められます。

松下
僕自身もこれまで金融機関や証券会社、士業などの提携パートナーと連携しながら、多くの承継案件に携わってきました。その中で強く実感しているのは、「誰がこの案件の“旗振り役”なのか」を明確にすることの重要さです。自らが軸となって全体の方向性を示し、先頭に立って案件をリードしていく。その覚悟と姿勢が、周囲の信頼を呼び、次の案件へとつながっていくんだと感じています。

SESSION.5
次世代の“事業承継コンサルタント”を育てるために

松下
今はまだ僕自身が多くの案件を担当していますが、将来的にはしっかりと後進に引き継いでいける体制を整えたいと思っています。事業承継は決して一人で完結する仕事ではありませんし、属人化させていては、組織としての継続性が生まれません。だからこそ、チームで承継案件に取り組める「仕組みづくり」が必要です。

岩永
事業承継って、技術的な支援だけじゃない。社長やご家族の本音に耳を傾け、会社の未来を一緒に描いていく。そのためには、知識も経験も、そしてなにより「人間力」が求められる分野。だから、育成には時間がかかるし、場数も必要。

松下
僕自身も、先輩の姿を見て学んできました。だからこそ、後輩にはなるべく早いうちから“本番の現場”に立ってほしいんです。だから今は、OJTのように現場に同行し、リアルな提案や対話の流れを肌で感じてもらうようにしています。実際に現場で教えるスタイルは、承継という分野ではすごく有効だと感じます。

岩永
うちの強みは、単なる“業務”として育てるんじゃなく、「姿勢」や「思考」を伝えていける土壌があること。これは、松下さんのように、現場で実践してきたメンバーがしっかりと教えてくれているからこそ成立しているんです。例えば社内研修制度「アイユーアカデミー」では、現場経験豊富な経験者が講師になり、リアルなエピソードと共に体系的に学ぶことができます。

松下
最近では、相続や顧問領域で成果を出しているメンバーが「次は事業承継にチャレンジしたい」と手を挙げてくれるケースも増えてきたと感じています。そういう意欲的なメンバーにこそ、どんどん経験を積ませていきたいですね。
将来的には承継アドバイザリー部門を少なくとも倍の人員規模に拡大したいと考えています。特に、営業的なアプローチができるメンバーが3人揃えば、かなり強いチームになると思っていて。今後は、医療法人やMBO(マネジメント・バイアウト)、スクイーズアウトといった、より高度で複雑な承継ニーズも増えてくると予想しています。そういった案件にも柔軟に対応できるように、スキルや経験の層を厚くしていきたいですね。

岩永
何より「この分野でやっていくんだ」という強い意志を持った仲間と、一緒に未来を切り拓いていきたい。社会の変化とともに、承継の在り方も変わっていくはず。その先頭に立って進化していける組織を、これからも目指していきたいですね。
SESSION.6
あなたも、経営者の“最後の伴走者”になれる

松下
事業承継の現場に立つたびに、「人の人生に深く関われる仕事だな」と実感します。この仕事の本質は、“会社を継がせる”ことではなく、“経営者の覚悟と想いに寄り添う”こと。数字や理屈だけでは進まない、葛藤や決断のドラマがそこにはあります。だからこそ、1件1件に全力で向き合う責任とやりがいがあるんです。

岩永
経営者にとっての事業承継は、単なる手続きではなく「人生の集大成」。資産や人、理念までも次の世代にどうつないでいくかを考える、非常に重いテーマです。だからこそ、僕たちは単なる「税務の専門家」ではなく、「人生の伴走者」としてのスタンスが求められる。これは他では味わえない仕事の醍醐味だと思います。

松下
事業承継の仕事は、AIにも代替できない“人の営み”が根底にあります。経営者の価値観や家族関係、社員への想い……。その一つひとつに耳を傾け、最適な選択肢を一緒に探していく。これは、まさに“人間にしかできない仕事”だと思っています。
経営の中枢に踏み込む分、覚悟は必要ですが、その分得られる学びや成長の幅もとても大きい。やる気があれば本当に面白い仕事に出会えるのが、アイユーコンサルティンググループの承継アドバイザリー部門なんです。

岩永
若いうちから「本質」に触れる経験ができるという意味では、これ以上のフィールドはないと思っています。責任も大きいけれど、信頼して任せる文化がある。それがアイユーコンサルティンググループの風土です。「誰のために働くのか」「何のためにこの仕事をするのか」。その答えを、事業承継の仕事はきっと教えてくれます。中小企業を未来へつなぐこと。それは、社会を守ることとイコールなんです。

松下
「経営者の“最後の大仕事”に本気で向き合い、支える」ーそんな仕事に誇りを持って取り組みたいという方と、ぜひ一緒に働きたいですね。





